- ホーム
- 岩国聖書宣教教会 牧師より
- 海外宣教紹介
- ※お知らせ
- 集会案内
- 礼拝
- 日曜学校
- 夕拝
- 【祈祷会の学び(2022年2月9日更新)】
- ・目標に向かって突き進む
- ・神の御子
- ・囚人の祈り
- ・いと高き方の御子
- ・古い自分を脱ぎ、新しい自分を着る
- ・信仰の成長
- ・イエス様を通して和解が成立した
- ・しもべを取り戻す
- ・クリスチャンホーム
- ・恵みにより救われた
- ・イエス・キリストの体
- ・最愛の方に受け入れられる
- ・イエス様の死
- ・最後の晩餐
- ・タラントのたとえ話
- ・パリサイ人
- ・婚礼の晩餐
- ・赦し
- ・祝福され、また、非難もされたペテロ
- ・神の国について
- ・安息日の主、イエス様
- ・癒し主、イエス様
- ・イエスさまの教え
- ・バプテスマのヨハネとイエス様
- ・モーセの死とヨシュアとの新たな始まり
- ・主を愛すとは
- ・祝福とのろい
- ・契約が更新された
- ・私のような一人の預言者をあなたのために起こされる
- ・神様からの指示
- ・私たちが果たすべき責任
- ・必要を備えて下さる神様
- ・聖い民
- ・一番大切な戒め
- ・モーセの十戒
- ・従順への道
- ・神様、私を探って下さい
- ・幸せな家庭
- ・私達の助けは主から来る
- ・感謝祭らしくなかった最初の感謝祭
- ・私は誓いを果たします
- ・幸いな人よ
- ・彼らは主に向かって叫んだ
- ・わがたましいよ、主をほめたたえよ
- ・主に向かって歌え
- ・神様の裁き
- ・永遠の支配
- ・全能者の陰に宿る
- ・あなたの心を頑なにするな
- ・壁に書かれた文字
- ・火の燃える炉
- ・忠実な者は報われる
- ・全てが生きる川
- ・生き返る骨
- ・新しい心
- ・真実な牧者
- ・見張り番
- ・元に戻る事が約束された
- ・ライオンから救われた
- ・偶像に頼った結果
- ・神様の働きに任命されたエゼキエル
- ・パウロの計画
- ・他の人の事を思いなさい
- ・従順に歩む人生
- ・神の栄光の為に生きなさい
- ・福音のメッセージ
- ・圧倒的な勝利者になるには
- ・御霊の導きによって歩むとは
- ・信仰によって正当化される(義と認められる)
- ・罪に対して死ぬ
- ・そのため正当化されなさい(義とされなさい)
- 婦人会
- 【(new)こども礼拝】
- 子ども賛美
- (毎日更新中!)日々のみことば
- 週報(きずな)・メッセージ・礼拝メッセージ(音声)・お知らせ祈りの課題・ワークシート
- 御言葉メロディー
- 証
- 岩国聖書宣教教会殉教の証し
- 心に響く詩画&証し&メッセージ紹介
- 特別集会(リバイバル)
- イベント告知&報告
- 2024 夏のきょうかいがっこう(VACATION BIBLE SCHOOL!)
- 2023 夏のきょうかいがっこう(VACATION BIBLE SCHOOL!)
- 2023 イースター集会招待状
- 2019年10.23 グレース・オーさんのピアノコンサートが開催されました。
- piano1
- piano2
- piano3
- piano4
- piano5
- piano6
- piano7
- piano8
- piano9
- piano10
- piano11
- 2019年クリスマスの⛪
- 2019年 VACATION BIBLE SCHOOL!(夏季学校)
- イースタースケジュール
- クリスマス集会&クリスマスの豆知識
- Thanksgiving Day(感謝祭)
- VACATION BIBLE SCHOOL!(夏季学校)
- アクセス方法
- リンク集
- お問い合わせ
エピローグ

藤岡さんの奥さんは、一月以内に、社宅から出なければならなかった。そのあと、実家に帰るかどうか、迷った。しかし自分の手一本で子どもふたりを育てながら、ご主人の伝道の遺志をつごうと決心した。
さいわい、国立岩国病院の給食係りの仕事があったので、そこに勤めるようになった。今までは幹部社員の若奥様であったのが、一転して、激しい労働につく身となった。
ボーマン夫妻は、本国の教会でぜひ子どもたちの告別式を開かせてほしいと言ってきたので、いったんアメリカに帰った。友人たちは、もう二度と日本に行かないで、アメリカで牧師をするようにと強くすすめた。
ボーマン氏の父親は、病が重く、いつ死ぬかわからぬ身であった。まだクリスチャンになっていないその父親は、ボーマン氏が日本に帰ると言って聞かないので、「お前は、親のわたしと日本人と、どっちがたいせつなのか」と、声をあげて泣いた。
ボーマン氏は、この事故以来、いよいよ日本を愛するようになった。この国の救いのために、子どもだけでなく、自分の命を失ってもかまわないと思った。そして、一月五日に再び岩国の土を踏み、さっそく、藤岡さんの奥さんにふたりの子どもの真紀ちやんと徹君を、新しい家族として自宅に迎えたのである。
…朝、子どもたちの学校に行く時間がくる。ボーマン夫妻とふたりの子ども、それから藤岡夫人は応接間にひざまずき、その日一日のために、互いに祈り合う。それから子どもたちはミセス・ボーマンの運転する車で、それぞれ幼椎園と小学校に送り届けられる。
午後、子どもたちが帰ってくる。さっそく彼らは、ボーマン氏のひざの上にかけあがる。ボーマン氏は、馬になったり、抱きしめてやったり、かつて自分の子にしてあげたと少しも変わらぬことをして、相手になる。
台所では、タ食のしたくのため、ミセス・ボーマンと藤岡夫人が忙しく働いている。時々、信じられないほどの大きな笑い声が聞こえてくる。どちらかが冗談を言って、また笑いのきっかけを作ったのであろう。しかし次の瞬間、ふたりは顔を見合せて涙ぐむ。子どもと夫を失った心と心が、瞬間に通じ合うのだ。そのような時、ミセス・ボーマンは、深い溜息をはきながら、「おお、主よ、日本の魂を救いたまえ」と口にする。ボーマン氏を中心に、今までにない伝道活動が進められるのは間もないことであろう。
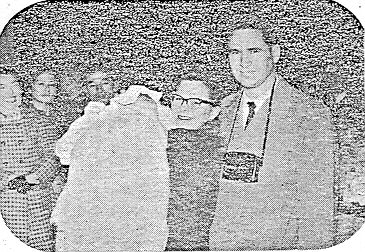
再帰国のボーマン夫妻